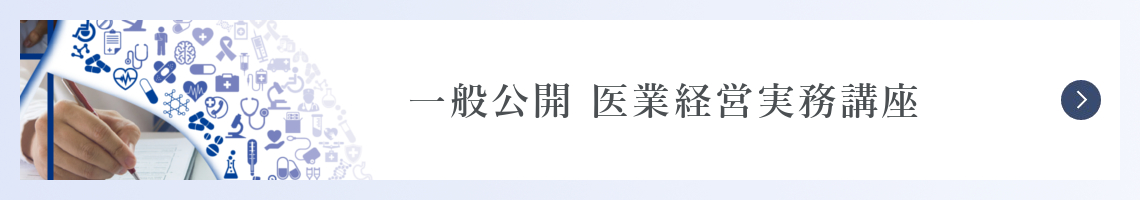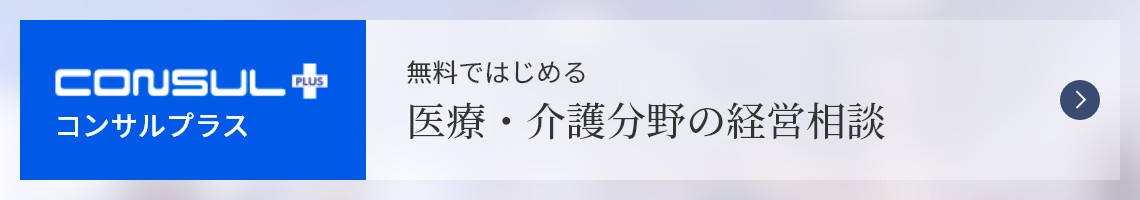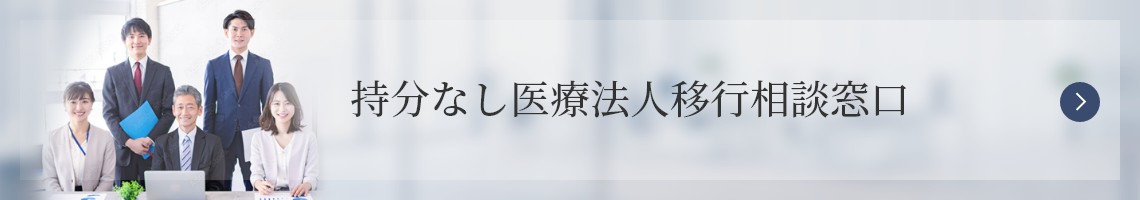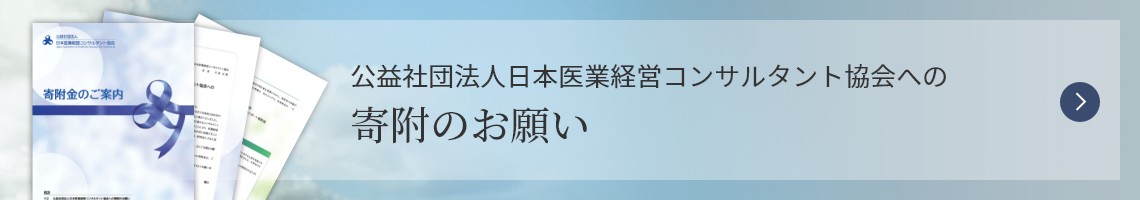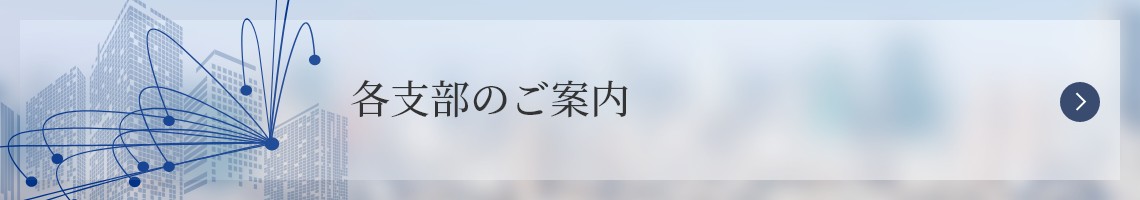用語解説 か行
この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。
高額療養費制度(2025年05月号掲載)
医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担額(食事療養費、保険外併用療養費の負担分は除く)が1カ月の上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度。上限額は、年齢(大きく70歳未満と70歳以上で区分)や所得(個人、世帯単位)で定められ、条件によってさらに負担が軽減される仕組みも設けられている。入院については、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる現物給付化の仕組みが、外来についても2012年4月から、同一医療機関で自己負担限度額を超える場合の現物給付化の仕組みが導入されている。
高額療養費制度は1973年10月、「医療の高度化により高額の自己負担を必要とする場合が少なくない」ことを踏まえて、当初は被扶養者のみを対象とする制度として創設された(注:老人医療費は1983年1月まで自己負担なし)。当初の上限額は、平均的な月給の50%程度となるようにと3万円で設定された。
その後、数次の改正の中で、低所得者の所得区分の設定、世帯合算方式、多数該当世帯の負担軽減、入院時の現物給付化、また外来特例の創設・現物給付化などの見直しが行われてきた。上限額は、所得水準が上昇する中で見合った水準の改正が行われず、2001年には平均的な月給の22%まで低下したため、2002年に25%に引き上げられ現行制度でも水準目安となっている。
高額療養費の支給金額・支給件数は、2021年度実績で約2兆8,460億円・6,198万件(「医療保険に関する基礎資料」より)。受給者数(ごく粗い2022年度ベースの推計値として公表)は、70歳未満が400万人(保険加入者数9,640万人)、70歳以上が850万人(同2,750万人)。
年々増加する高額療養費の総額(総医療費の6~7%相当)が医療保険財政に大きな影響を与えているとして、「セーフティネットとしての高額療養費の役割を維持しつつ、健康人を含めたすべての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図る観点からの見直し」が社会保障審議会医療保険部会で議論され、2025年8月から所得区分の細分化、自己負担限度額の引き上げが行われる予定だったが、国会予算審議の中で議論の的になり、2025年3月に現行制度(2018年度改正)の見直しの見送りが決定している。
 お問い合わせ
お問い合わせ